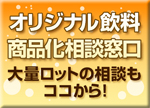こだわりの「瓶入りサイダー」に地域の物語を詰めて
地サイダー 復刻・誕生物語
地サイダーで名を馳せる、九州は佐賀の友桝飲料(小城市)。「瓶入り」「昭和レトロ」をコンセプトに、古くて新しい風合いのサイダーづくりで人気を集めている。オリジナル地サイダーに加え、これまでに十指を超える地サイダーを受託製造してきた。その真骨頂は、「地域の物語」を織り込んだ商品開発だ。
視覚で手に取らせる「昭和レトロ」の吸引力
瓶、王冠の蓋、ラベル。商品を包み込む要素はすべてレトロ調。昭和生まれならずとも、懐かしさに駆られる――。
友桝飲料オリジナルの地サイダーである「スワンサイダー(復刻版)」や「謹製サイダァ」はいま、サイダーの枠を超え、鮮やかな存在感を放つ。雑貨ショップや家具店を飾る一品として使われるなど、その付加価値は飲むシーン以外でも評価されている。
地サイダー全盛期の味を再現した同社のサイダー。ターゲットはサイダーやラムネを飲んで育った年齢層に定めていた。
一方で「ただ『古くさいもの』で終わらず、若い人たちには新しく見えるようデザインにはこだわった」と同社の友田諭社長は語る。

昭和を懐古趣味的に捉えるブームがここ数年、続いてきた。2005年公開の映画、『ALWAYS 三丁目の夕日』のヒットも一例だろう。この現象は、戦後から高度成長期を肌身で知らない世代にも及んだ。若者の間では昭和の風合いを持つ商品に興味を示す動きが生まれた。
そんな時代の求めに同社の地サイダーは見事に合致した。
「スワンサイダー(復刻版)」は当初、業務用限定で開発・発売したにもかかわらず、現在では関東・関西の都市部百貨店や高級スーパーで常備されるなど、レトロを志向する消費者の間で確かにファンを得ている。
消え去るもの食い止める意志 使命感からブランド復刻へ
「スワンサイダー」自体は、友桝飲料が80年近くの間つくり続けてきたもの。いわば同社の看板商品だったが、現在の形に「復刻」されたのは05年のこと。まだ地サイダーという言葉は一般に馴染みはなかった。
この頃、瓶入りサイダーというジャンルは「放っておけば消えてしまう」(友田氏)状況にあった。
01年に4代目として社長に就任した友田氏の胸にあったのは「ウチがつくらないと残らない」という使命感にも似た思いだった。
中小の清涼飲料メーカーの経営者はおおむね50〜80歳代。若い経営者が動かなければ――。「自分がラムネ、瓶入りサイダーで育ったせいか、どうしても瓶にこだわりたかった」と友田氏は振り返る。
04年から検討を開始した復刻は、その強い思いにもかかわらず、セールス面での自信はほとんどなかった。「売らんかな」の野心もなかった。ただ「残したい」という一念だけがあった。
だが使うべき瓶はもうなかった。新たに瓶メーカーに製造を発注した。本数は30万本。小ロットでの対応は得られず、そうするしかなかった。「スワンサイダーは年間1万本もつくればいいほう」(友田氏)にもかかわらず、だ。瓶でこそおいしいサイダーを飲んでもらえる。その信念があった。
瓶を確保すれば、あとは昔日のレシピに従って製造するだけだった。サイダーの原料は水、炭酸、砂糖、香料のみ。いたってシンプルだ。糖分は昨今、人工甘味料を使うメーカーも多いが、100%砂糖にした。砂糖を使うと「スッキリとした上品な飲み口になる」(友田氏)からだ。
また、強めの炭酸も忠実な再現を目指してのことだった。こういった丁寧な商品づくりがあって、「スワンサイダー」の復刻がなった。

工場の稼働率向上がきっかけ
01年の社長就任時、地サイダーの受託製造はまだ事業として存在していなかった。しかし事業の芽はこの時期に育まれた。当時友田氏が目前の課題としていたのは、工場の稼働率向上だった。
「夏は自社ブランドがある程度は売れる。ただ秋冬に入ると工場の稼働が週2〜3回に落ちる」
装置産業であるだけに、稼働率の低下は会社にとって死活問題だ。「遊んでしまう工場をどうにかできないか」と考えを巡らせた。大手ブランドの下請けとして何万、何十万という規模で製造する中小の清涼飲料メーカーは数多い。だが小ロットでの受託製造はほぼ皆無だった。
「個人経営の飲食店、自治体や地域の団体の企画を扱うメーカーはない。チャンスだと思った」(友田氏)。工場がコンパクトなため、小ロットの受託製造に適している。
こうして「商品化サポート事業」を打ち出した。試行錯誤する中で、福岡の飲食店から受託製造の依頼が舞い込んだ。その店では、ビールのように見える同社の炭酸飲料「スワンガラナ」のラベルをはがし、“こどもビール”という名前で自らラベルを制作、貼り直していた。しかし手間がかかりすぎるため、正式に「メーカーでつくってほしい」となった。
こんな経緯があって03年に製造を開始した「こどもびいる」はその後、「ビール様清涼飲料」という新市場を形成、人気商品となった。
それまで九州・四国・中国に限られていた商圏は、全国へ広がった。販路の拡大は、05年に発売する自社地サイダー「スワンサイダー復刻版」登場の地ならしになった。

「この事業で営業はしない」それでも増える引き合い
現時点で、友桝飲料の事業全体から見ると、地サイダーの受託製造事業が売り上げにしめる割合は1割程度。だが数字だけでははかれない効果がある。一般的な知名度の向上は、社員の意識を高めているのだ。
「自社ブランドのサイダーで必死にやってきた結果、ブランディングのノウハウ伝授も含め、受託製造を事業の柱にできるまでになった」と友田氏は語る。「商工会など、地域の団体から『地サイダーづくりに協力してほしい』という引き合いは増えている」
地域おこしの熱意を負う地サイダーだが、つくり手として友田氏は「熱意」を最重視している。「つくりたい」という地元の熱意がない限り、地サイダー事業はできないと考えるからだ。
だから地サイダーの受託製造のため、営業をかけることはない。引き合いはまさに自然と増えてきた。これが実感だ。「熱意不在のところに押しかけて営業してもうまくいかないだろう」(友田氏)

熱意を踏まえ、さらに「地」の奥深くへ踏み込む。これが友桝流だ。地元の特産品のみならず、歴史や風土を深く掘り下げ、それを商品に、あたかもサイダーの中身液のように充填する。
「楽につくろうと思えば地サイダーは簡単にできてしまう」と友田氏は話す。既存の地元のサイダーを、ラベルを貼り替えて売り出すだけでよいのだという。
だが「消費者の肥えた目はだませない」とも指摘する。「小細工だけでつくったものは買ってもらえない。付加価値として感じられる『ストーリー』がなければ、底の浅さを見られてしまう」
初の受託生産から一貫 地域の物語を「充填」
細部まで目を配る友桝飲料のサイダーづくり。そのスタイルは初の地サイダー受託製造のときから変わっていない。
’05年、長崎の雲仙旅館ホテル協同組合から依頼を受けて開発をスタートさせた「温泉レモネード」は、忘れられていた郷土史を柱とした。
翌年の商品化・発売にこぎ着けるまで、一年を費やした。「雲仙には何度も足を運んだ。初期投資としては完全に赤字だった」と友田氏は笑う。
しかし作業そのものは充実していた。直接の依頼者である組合理事は郷土史に精通していた。
明治期の雲仙は世界に開かれた長崎港から近く、避暑に訪れる外国人が多かった。彼らに供するため、ラムネがつくられていた。
作家パール・バックをイメージした女性を描いたラベルも、彼女が雲仙に滞在したという史実の掘り起こしを通じて決定された。
こうして雲仙温泉の天然水を100%使用、雲仙産のレモン果汁を加えた「温泉レモネード」が誕生した。
「ただつくるだけでなく、地元の商品として根づかせるノウハウを伝えたい。数年後になっても消えていないように」――。友田氏の思いが強く込められた印象深い一 品となった。
つくるのは「自分が欲しいもの」
友田氏が商品開発の根幹に据えている原則がある。それは「自分が欲しいものをつくる」というものだ。シンプルではあるが、ものづくりの一つの基本を的確に言い表した言葉だろう。
たとえば多くの人が目的のある「指名買い」で訪れるコンビニ。そこでも友田氏は絶えず「自分が欲しいものが何かないか」と目を光らせている。そしてその場で「買いたい」と思えるものを買う。この積み重ねのうちに「欲しいもの」に対する意識は透明度を増し、次なる商品像が見えてくる。
「せっかく訪れた観光地でどこでもあるものを買いたいと思う人は少ない。清涼飲料にしてもそう。地域の特性を活かさなければ」
商品づくりの面では、友桝飲料で受け継がれてきた進取の気性も見逃せない
創業者である大祖父の友田桝吉氏は友桝飲料を1902年に創業、「こんな田舎でラムネをつくろうとしたほど、変わった人間だった」(友田氏)という。2代目で祖父の軍平氏は他社に先駆けて人 工着色料を天然着色料に変えるなど、先見の明のある人物だった。
「祖父からは『面白いこと、新しいことをやらないといかんよ』と言われて育った」という友田氏。物静かな印象も受けるが、使命感でサイダー復刻へと突き進んだ実績は、やはりDNAを感じさせる。

飲料の一ジャンルへ
地サイダー事業を打ち立てた友田氏は次のステップを見据え、「将来的には地サイダーが地酒、地ビールのように、飲料の一ジャンルとして確立されるようにしたい」と語る。「スワンサイダー(復刻版)」で得た手応えは確かなものだ。
意欲を見せる友田氏だが、そこに驕りは微塵も感じられない。
「地サイダー事業は、地域振興を図る自治体の政策に運良くマッチした面もある」とすら言う。
控えめなこの姿勢は、過剰な自己主張のない商品づくりに通底するようだ。そしてその程よい抑制こそ、新商品が洪水のように流れ出てくる時代には新しい。
そんなセンスと地域を思う商品づくりのノウハウを武器に、友桝飲料はおいしさのわき出す地サイダーをつくり続けていく。
Company Profile
- 友桝飲料
- 佐賀県小城市牛津町牛津834
- 従業員 40人
- 資本金 3000万円
- TEL:0952-66-0062
- http://www.tomomasu.co.jp/
Copyright © 2009 記念品ソーダ. All Rights Reserved.